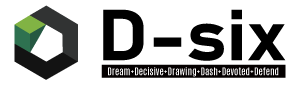スマートフォンを手に取る度に、重たいニュースが飛び込んでくる。
戦争、自然災害、経済危機…。「また何か起きたのか」という疲れた思いと共に、なんとも言えない不安が心の奥に溜まっていく。そんな経験、誰もが持っているのではないでしょうか。
見えない不安との付き合い方
先日、40代の会社員Bさんがこんな相談をしてくれました。
「夜、子どもが寝静まった後にニュースをチェックするのが習慣だったんです。でも最近は、見るたびに心が重くなる。戦争のニュースを見れば『この先どうなるんだろう』って不安になる。経済ニュースを見れば『家族を守っていけるのか』って考えてしまう。でも見ないと取り残される気がして…」
この言葉に、私は現代人の抱える深い矛盾を感じました。情報から逃げられない。でも、情報に押しつぶされそうになる。この板挟みの状態は、実は脳にとって大きなストレスとなっているのです。
「知ること」の代償
人間の脳は、かつて身近な範囲の情報だけを処理すれば良かった時代に作られています。今私たちは、地球の裏側で起きた出来事まで、リアルタイムで知ることができます。これは素晴らしい技術の進歩ですが、同時に私たちの脳には大きな負担となっているのです。
悲しいニュースを見るたび、私たちの脳は「共感性ストレス」を感じます。他人の苦しみを自分のことのように感じ取る能力。これは人間の素晴らしい特徴なのですが、グローバル化した情報社会では、この能力が仇となることもあるのです。
心を守るための、新しい習慣
ある研修医との会話が印象に残っています。彼は言いました。 「救急外来では、自分にできることとできないことを、明確に区別することを学びます。それが、長く現場で働くためのコツなんです」
この言葉は、情報過多の時代を生きる私たちにも、重要なヒントを与えてくれます。
世界で起きるすべての問題を解決することは、誰にもできません。しかし、自分にできる「小さな一歩」はあるはずです。例えば:
身近な人を大切にすること。 自分の生活圏での小さな貢献をすること。 必要な時に必要な支援をすること。
このような具体的な行動に集中することで、漠然とした不安から解放されることがあります。
情報との新しい付き合い方
ニュースを見る時間を決める。これは意外と効果的な方法です。「朝15分」「夜の30分」など、時間を区切ることで、脳は「今は情報を受け取る時間」と「それ以外の時間」を区別できるようになります。
また、信頼できる情報源を2~3つに絞ることも有効です。情報の質を重視することで、不必要なストレスを減らすことができます。
希望は必ず見つかる
歴史を振り返ると、人類は常に危機と向き合ってきました。そして、その度に新しい解決策を見出してきたのです。
実は、重大なニュースが報じられる裏で、必ず希望につながる動きも起きています。戦争の影で、平和に向けた地道な努力が続けられ、災害の後には、人々の絆が強まっていく。
私たちにできることは、この希望の種を見つけ、育てていくことなのかもしれません。
あなたへのメッセージ
情報に振り回されない。でも、現実から目を背けない。 この難しいバランスを取ることは、現代を生きる私たちの課題なのかもしれません。
今夜、ニュースを見る前に、深いため息をついてください。そして思い出してください。 「私にできること」と「私にはできないこと」があること。 そして、「できること」に集中することから、新しい一歩が始まることを。